待機児童問題の解決を原点に、企業主導型保育園を立ち上げた松尾氏。保護者の負担を軽減する“手ぶら登園”や365日開園といった仕組みを整え、子育てと仕事の両立を後押ししてきました。海外での起業経験から培った行動力と、弁当店での現場経験から学んだ「誠実さ」を胸に、今では地域全体の安心と成長を見据えた活動を展開しています。保育園運営にとどまらず、フランチャイズによる自立支援、防犯カメラ設置による地域の安全確保など、事業の枠を越えた取り組みを推進する松尾氏のビジョンを伺いました。
保護者に寄り添う保育園づくり
まず、現在取り組まれている事業の内容や特徴について教えてください。
今は企業主導型保育園を2園運営しています。対象は0〜2歳児で、定員はそれぞれ19名と12名です。立ち上げのきっかけは、宮若市で待機児童が約130人発生していたことでした。人口約2万6000人の街でこの状況を知り、「子どもたちが安心して預けられる環境をつくろう」と考えました。園の特徴は、園児だけでなく保護者にも寄り添う仕組みを徹底している点です。朝7時〜夜20時の通常保育に加え、22時まで延長保育に対応し、365日(日曜・祝日含む)開園しています。保育料は一律でわかりやすく、オムツやおしり拭き、給食費などの追加負担はありません。スモックや給食セット、お昼寝セットも園で用意するため、ブランケットだけ持ってきてもらえれば“手ぶら登園”が可能です。荷物の準備や名前書きの手間を減らし、保護者の負担を大きく軽減しています。
保育園立ち上げ以前、シングルマザー・ファザー向けのシェアハウスを運営されていたとのことですが、その経験はどのように影響しましたか。
全国から移住してくださる方が多く、「待機児童が多い地域では働きにくい」という声をお聞きする中で、保育の重要性を実感しました。認可保育園は申請手続きの都合上、移住者にとって不安が残る面がありますが、企業主導型であれば園側で入園確定を出せるため、移住や就労をスムーズに進められます。そうした自由度の高さが、私たちが企業主導型を選んだ理由です。
現在2園体制とのことですが、その経緯を教えてください。
感染症の流行期を踏まえ、共用部の多いシェアハウスの運営は一旦集約しました。その建物を改装し、2園目「ぽたぽた園2」として活用しています。こうして保育の受け皿を広げることで、地域の子育てと働き方を支える体制を整えてきました。
海外から始まったキャリアと経営者としての原点
これまでのキャリアについて教えてください。
高校卒業後、オーストラリアに留学しました。語学学校を経てグリフィス大学に進み、卒業後は現地で友人と起業しました。ちょうど日本でメラミンスポンジが流行していた時期で、「激落ちくん」のような商品がオーストラリアにはまだなかったんです。そこで日本のサプライヤーを探し出し、独自ブランドで輸入・卸を行い、全国規模に展開しました。テレビショッピングにも商品を出したほどです。
ただ、永住権が取れずオーストラリアでの生活を続けるのが難しくなり、共同経営していた仲間たちと話し合い、株式を売却して帰国しました。帰国後は父が経営していた弁当チェーンの1店舗で店長を務め、そこで出会ったシングルマザーの大変さを目の当たりにしたことが、後のシェアハウス立ち上げや保育園設立につながりました。地方創生を意識した「住まい・保育・仕事の3点セット」を軸にしたビジネスモデルを福岡よかとこビジネスプランコンテストに応募したところ大賞をいただき、それをきっかけに銀行融資も進み、保育園の立ち上げに至りました。
学生時代から経営者になる意識はあったのでしょうか。
そうですね、チャンスがあればいつでもやりたいと思っていました。大学卒業後、日本に一度帰るタイミングで就職活動もしていましたが、面接の場で「やりたい事業計画がある」と話したら「だったらそちらをやった方がいい」と言われたんです(笑)。その一言で背中を押され、日本で準備をしてから再びオーストラリアに戻り、起業に踏み出しました。
実際に経営をしてみて、どんなギャップや気づきがありましたか。
大学では「1億円の予算でマーケティングプランを考えなさい」という課題がよく出ましたが、実際に会社を始めたときには資金がほとんどないところからのスタートでした。そこは大きなギャップでしたね。最初は3人で始め、1年後には4人になり、それぞれ200万円をどうにかして集めて立ち上げました。
資金が限られているため広告費をかけられず、商品のサンプルを報道番組などに送りました。ちょうどオーストラリアで「水だけで汚れが落ちるマイクロファイバークロス」が人気になっていた時期で、その100倍細かい繊維を使ったメラミンスポンジを紹介したらニュース番組で取り上げてもらえたんです。まだ販売先がない状態で全国ニュースになり、問い合わせが殺到しました。その映像を持ってスーパーなどに営業に行き、「消費者が探している商品です」と伝えることで販路を広げられました。資金がないからこそ工夫し、チャンスをつかめた経験だと思っています。
正直さが生む信頼の組織づくり
経営をする上で大切にされていることは何でしょうか。
大事にしているのは「変に取り繕わない」「ごまかさない」という姿勢です。弁当屋の店長をしていた頃、ピーク時には多くのお客さんを待たせてしまうことがありました。あるとき、揚げ物を落としてしまい、あと数分で仕上がるはずのお弁当をさらに作り直さなければならなくなったんです。そのときにどう説明するか、非常に迷いました。
そのときどのように対応されたのですか。
先輩店長のエピソードを思い出しました。その方は同じ状況で「たった今、白身フライを落としてしまいました。申し訳ありません。揚げ直しますので、さらに3分お待ちいただけますか」と正直に伝えたそうです。すると、お客様は「あと3分待てばいいんだ」と納得され、怒りが和らいだといいます。私はその話を聞いて、失敗したら正直に伝え、誠実に対応する方が結果的に信頼につながると学びました。
その経験は現在の経営にも影響していますか。
はい。あのときの学びは今の事業にも通じています。失敗を隠そうとすると事態は悪化しますが、正直に伝えれば理解を得やすく、その後の信頼関係も築けます。社員や保護者の方に対しても、問題が起きたら率直に共有し、解決に向けて一緒に考えるようにしています。ごまかさずに向き合うことこそ、組織の健全な運営と人とのつながりを強くする大切な姿勢だと思っています。
未来への展望と社会貢献への挑戦
今後の展望について教えてください。
フランチャイズ化によってシングルマザーやファザーの方々もオーナーになれる仕組みを整えていきたいと考えています。最初は店舗の店長として経験を積み、黒字化できたタイミングで経営を引き継ぐ。リスクを抑えながら独立できるようにすることで、「頑張りたい人が頑張れる社会」を支えたいという法人理念を実現していきたいと思っています。
フランチャイズ以外にも、新たに取り組もうとされていることはありますか。
はい。今後は保育園に限らず、地域で頑張る人たちの障害を取り除く事業を展開していきたいと考えています。例えば「働きたいけれど子どもを預ける場所がない」という課題に保育園で応えてきたように、別の領域でも同じように支援できる仕組みをつくりたい。
具体的にはどのような構想があるのでしょうか。
今、宮岡市でも不審者情報が頻繁に流れる状況があります。行政や警察の対応はどうしても「事件が起きてから」になりがちなので、地域として先回りして安全を守りたい。そこで市内に防犯カメラを100台設置する計画を立てています。弊社から10台を寄付し、残りは協賛やクラウドファンディングで賄う予定です。
海外から直接輸入してコストを抑え、地域の電気会社さんも無償で設置に協力してくれることになっています。利益を生む事業ではありませんが、地域全体の安心につながる取り組みとして進めていきたいと思っています。
「社会の障害を取り除き、頑張る人を応援する」ことを軸に、保育事業にとどまらず、地域貢献を広げていくのが私たちの未来へのビジョンです。
家族と歩む日常と、未来の子どもたちへの願い
経営以外で、没頭されている趣味などはありますか。
趣味に費やす時間はほとんどなく、子どもが6人いるので、休みの日は必ずどこかに連れて行って遊ばせる“ミッション”があります。一番下は1歳になったばかりで、上は中学1年生。にぎやかな毎日で、自分の時間というよりは子どもたちと過ごす時間が中心になっています。
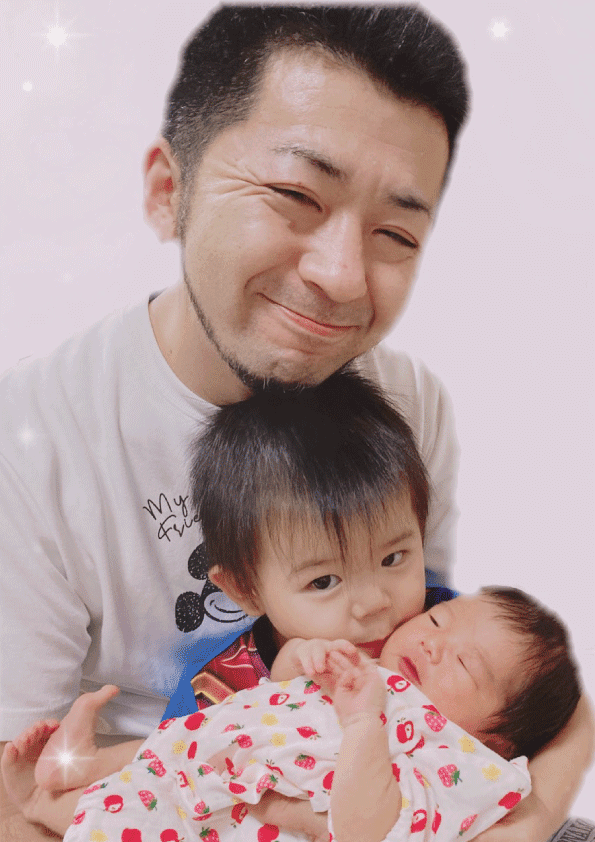
学生時代や若い頃には、どんなことに打ち込んでいましたか。
小学生の頃は将棋をやっていて、全国大会で4位になったことがあります。中学では卓球をしていましたが、それほど成績は残せませんでした。留学先では大学の野球チームに入り、オーストラリア・クイーンズランドの大会に出場。始めて2か月ほどでしたがベスト9に選ばれ、セカンドベースを守りました。あのときは本当に良い経験でしたね。
最後に、経営者の方々やこれから経営を目指す方々へメッセージをお願いします。
私より大先輩の経営者の方が多いと思いますが、今、日本全体で子どもたちの安全が脅かされています。全国で毎年1000人以上の9歳以下の子どもが行方不明になっており、さまざまなリスクが背景にあると考えられています。ニュースでも不審者や誘拐未遂が取り上げられていますが、地域の子どもたちを守るための取り組みはまだ十分とは言えません。
私は今、防犯カメラ100台の設置を目指すプロジェクトを進めています。小さな取り組みかもしれませんが、抑止力として必ず意味があると信じています。そして全国的に広がれば、子どもたちが安心して過ごせる環境につながるはずです。
経営者の皆さまのお力添えがあれば、この流れをさらに大きくすることができます。もし関心を持っていただけるようでしたら、ぜひご協力をお願いしたいと思います。








