絶対価値×サステナブル×レジリエンス――139年企業が挑む「自立分散型」の未来
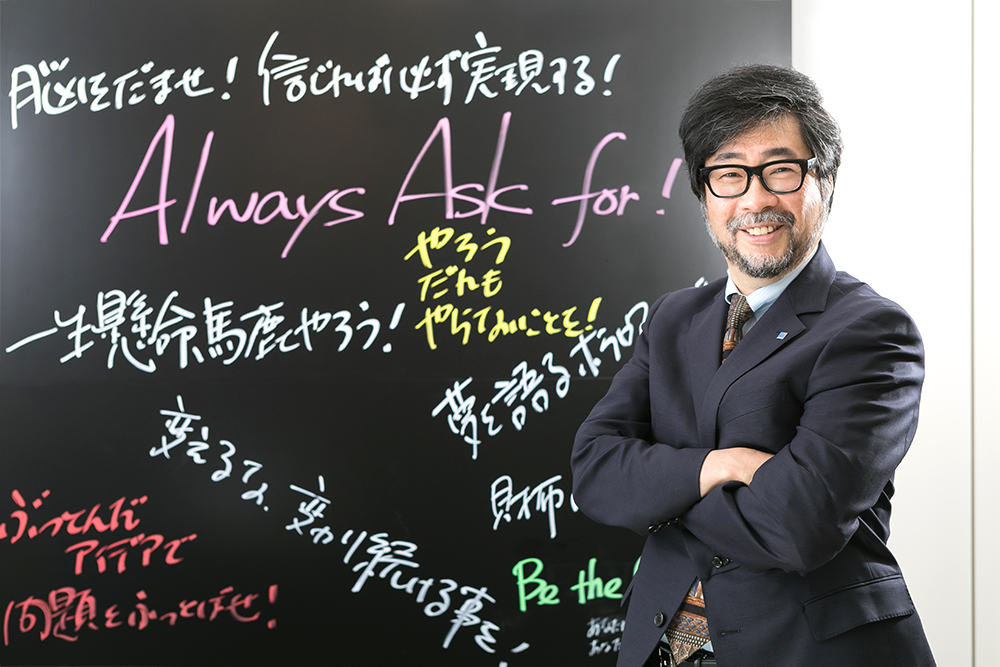
株式会社カクイチ 代表取締役社長 田中離有氏
株式会社カクイチは、創業139年を迎えた老舗企業です。ガレージやホース、太陽光、ナノバブルなど多角的な事業を展開しながら、「自立分散型のネットワーク」で社会の持続性と回復力を高める取り組みを進めています。 田中離有社長が掲げるのは「絶対価値×サステナブル×レジリエンス」。予測不能な時代に、企業も個人も“自ら考え、つながる力“が問われる今、そのビジョンと実装について伺いました。
目次
社会のインフラを担う企業としての使命
――現在の事業内容と理念について教えてください。
当社はもともと金物問屋からスタートしガレージやホースなど、いわゆる“ものづくり企業“として展開してきました。ところが、東日本大震災を契機に、中央集権型の仕組みの脆さを目の当たりにし、電力の「自立分散型」の必要性を痛感しました。そこで始めたのが太陽光事業です。平時は環境価値を、非常時は命と暮らしを守る機能を——この二面性を持つ仕組みづくりを進めています。
具体的には、当社が売ったガレージの屋根を「再生可能エネルギーの発電拠点」に変えるモデルです。当社が売ったガレージは全国に8万棟以上あります。その屋根の上に太陽光パネルを乗せれば、地面を使わず土地を殺さず、平時の脱炭素と非常時の電源確保が両立できます。この取り組みは7年間で約17,000件・136MWまで拡大しました。
人が生きていくのに必要なのは、電気(エネルギー)、食料・水、そして助け合う仲間です。中央集権の仕組みが止まっても地域で回る「自立分散型ネットワーク」を広げることが、今のカクイチの使命だと感じています。
父から受け継いだ「創業者の直観」とMBAで見えた「相対価値」の罠
――経営者としての原点やキャリアの転機について教えてください。
私は4人兄弟の末っ子で、大学卒業後は自動車部品メーカーに勤めていました。しかし「外の世界を知らずに家業を継ぐのは違う」と考え、アメリカのジョージタウン大学に留学しMBAを取得しました。 帰国後に家業へ戻りましたが、バブル崩壊後は経営が思うようにいかず苦労しました。数字や競争で測るMBA的な「相対価値」では業績は回復しなかったんです。
転機は、創業者の理念に立ち返り、父が体現した「絶対価値」を見直したこと。父は周りがどうあれ、自分の理念信念を大切にしていました。それは“人の心を豊かにする価値“を追求した経営です。当社は創業当時から「正札販売」「カンバン方式」「品質保証」を掲げており、当社の製品を買ってくれたお客様には、たとえそれが小僧さんでも大切にして来ました。私たちは「創業者の考えに戻る」ことで、効率的だが脆弱な相対価値経営から、環境が変わってもぶれない“軸”を持つ絶対価値経営へと舵を切りました。
自律分散型の組織運営――「失敗を許す文化」が育む主体性
――社員との関係づくりや、組織運営で意識していることはありますか。
2019年に「情報を現場に開放する」組織改革を行いました。中間管理職を介して伝えるのではなく、経営層と現場が直接つながる仕組みです。Slackを導入し、社員が自由に意見を発信できるようにしました。同時にミッション・ビジョン・バリューを書き換え、現場が自ら考え挑戦する組織文化の醸成を目指しました。“命令“ではなく“共感“で動く組織です。
特に大事にしているのは「失敗しても学ぶ組織」をつくることです。上からの指示では人は成長しません。自分の意思で動き、仮説を立て、失敗から学ぶ経験が会社の財産になります。
また、女性社員の登用にも積極的です。年功序列にこだわらず、実力があれば20代でも執行役員になれる。挑戦できる環境を整え、社員一人ひとりが自律的に動く“OODA型組織“を目指しています。
「自律×分散」が導く次世代社会への挑戦
――今後の展望をお聞かせください。
目指しているのは、地域が自ら回復する“レジリエンス“と、日々続いていく“サステナビリティ“を両立させること。そのために、エネルギー・水(ナノバブル等の水インフラ)・農業・DXを結び、自治体や企業とともに自立分散型のネットワークを広げていきます。
アクアソリューション事業では、水の循環を軸に農業や畜産、環境保全まで領域を拡大しています。エネルギー事業では、自治体や企業と連携した脱炭素スキームを構築中です。DX分野でも、他社とノウハウを分かち合いながら、「ともに進化する産業構造」をつくりたいと考えています。
壊れたものを直す時間が、思考を整える
――仕事以外でのリフレッシュ方法を教えてください。
古い車を直すことが一番の趣味です。50年近く前の車は必ずどこか壊れていますが、原因を探り、パーツを取り寄せ、少しずつ直していく過程が面白い。そうするとデザインを手がけた人の想いにも触れられる。まるで“対話“しているような感覚です。
手を動かしていると脳が整理され、次の発想が生まれる。経営も同じで、壊れているものほど再生のチャンスがある。直しながら新しい価値を見出していく――その姿勢が私の人生そのものです。
最後に 老舗企業の使命は「守ること」ではなく「進化し続けること」。「絶対価値(Why)」を追求する企業こそ、「サステナブル(How)」と「レジリエンス(What)」を備え、真の“100年企業“になれると信じています。地域とともに、次の100年をつくっていきます。












