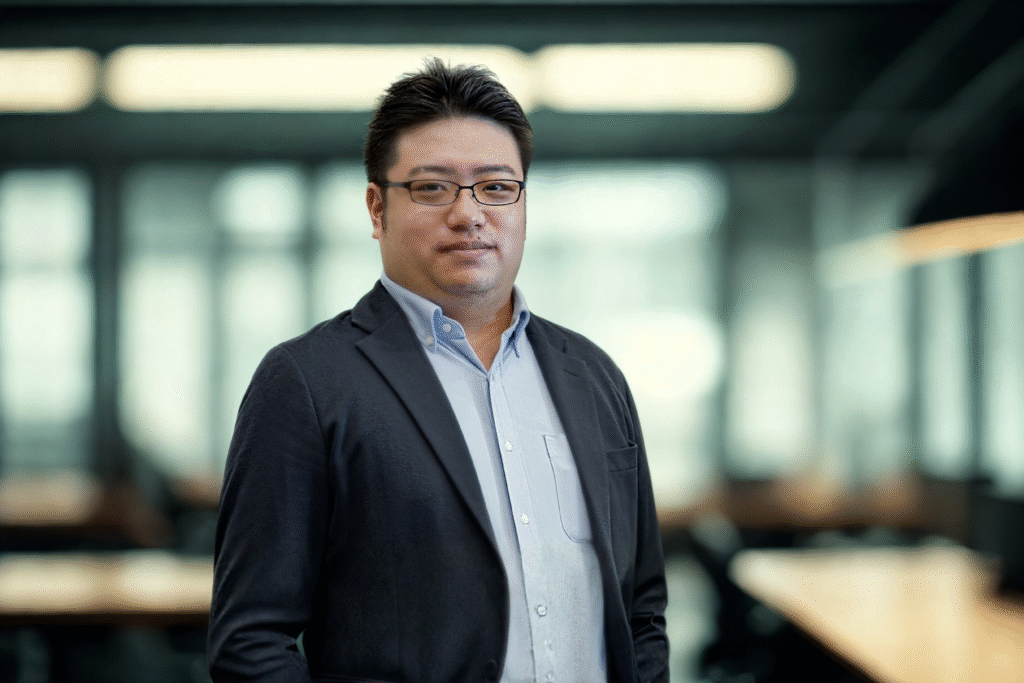Geniusyst株式会社は、AIやクラウド技術の研究開発とシステムの受託開発事業を両軸に、テクノロジーの力で社会課題の解決に挑んでいます。
代表の荒木雅樹氏は、中学時代から「自分の手で革新的な次世代のコンピュータをつくりたい」という夢を描き続け、その探究心のまま大学在学中に起業の道へ。現在は、研究と実装を往復しながら、技術で社会に価値を生み出す企業づくりを進めています。
経営を通じて学んだ人と組織の在り方、今後のビジョン、そして“ものづくりを楽しむ心”について伺いました。
目次
独自の研究とシステム開発、2軸で進化する事業モデル
まず、御社の事業内容と特徴について教えてください。
弊社は大きく「ベンチャー領域」と「システム受託開発領域」の2軸で展開しています。ベンチャー領域では、私が大学在学中から取り組んできた人工知能やクラウドコンピューティングを基盤に、自社で製品と技術の両方を研究開発しています。公的な支援プログラムやベンチャーキャピタル、金融機関からのサポートをいただきながら、社会を大きく変える新たなコンピュータモデルの開発を目指しています。
受託開発のほうは、どのような体制なのでしょうか。
研究だけでなく幅広く社会に貢献できる形として受託開発事業を並行して展開しています。現在は会社全体の約8割を占める主力事業です。フルスクラッチ開発にも対応できますが、弊社では「ノーコード開発」を強みにしています。優秀なエンジニアが在籍しており、たとえばBubbleなどのツールを活用し、短納期・低コストながら高い自由度を実現しています。Bubble認定エンジニアも在籍しており、データベースなども含め、設計・構築の深い部分まで踏み込んでの開発ができるのが特徴です。
エンジニアの方々はどのような方が多いですか。
実務経験豊富なベテランが多く、私より年上の方が中心です。ただ、年齢に関係なくチャレンジ精神が旺盛で、新しい技術や未知の領域への探究を楽しむ人たちが集まっています。要件定義から開発、テストまで一人で完結できる高いスキルを持ち、純粋に“ものづくりが好き”という気持ちで動いているメンバーばかりです。
会社として大切にしている理念を教えてください。
「技術を通して社会に新しい価値を生み出すこと」です。自社研究開発と受託開発の両輪で、より良い社会の仕組みをつくる。そのために、挑戦を恐れず、探究心をエネルギーに変える組織でありたいと考えています。
自ら動き、仲間と築いた挑戦の軌跡――荒木雅樹のキャリア
中学時代から起業を志していたとのことですが、具体的にどのようなキャリアを歩まれたのでしょうか。
電気工事士だった祖父の影響もあり、幼少の頃から電気・電子の分野に強い興味を持っていました。中学生の頃には独自のコンピュータモデルを構想し、「将来は自分の設計した革新的なコンピュータを世に送り出すんだ」という意志のもと、同時に起業を志しました。そこから技術はもちろん経営についても学び、大学では起業家育成教育プログラムに参加。大学3年のときに中退し、1年間は会社の運転資金を貯めるために働き詰めの日々を送りました。正社員やアルバイト、日雇いなど4つの仕事を掛け持ちし、ほぼ24時間フル稼働で資金を確保しました。その後、Geniusystを創業。就職して経験を積むというより、自分の信じた道をカタチにするために動き続けたようなイメージです。
実際に経営者になってみて、イメージとの違いはありましたか。
当初は「社長=会社のトップで指示を出す人」という漠然としたイメージを持っていました。しかし実際は、会社そのものが“生き物”のようで、自らが動き続けなければすぐに全てが止まってしまう。仕組みづくりや営業、開発まですべて自分が担う必要があると気づきました。責任も重いですが、その分だけ自分の意思で舵を切れる面白さも感じています。
会社の成長において、人とのつながりはどのように広がっていったのでしょうか。
高校・大学時代から「将来はこういうコンピュータをつくる」「会社を設立して、革新的な製品を世に出すんだ」と周囲に語り続けていたことで、自然と志を共にする仲間が集まりました。個人事業として創業したばかりの苦しい時期にも、取引先の方が「面白いことをしているね」と声をかけてくださり、それが新たな出会いへとつながっていきました。
大学時代の経験も大きかったと伺いました。
熊本の大学在学中には、学生が将来の起業を目指して活動する起業家育成教育プログラムに参加していました。そこでは同世代の仲間と共にビジネスプランを練り、社会で実践できるアイデアを形にしていく経験を積みました。こうした挑戦の積み重ねが、現在の事業や人脈の礎になっていると思います。
仲間と共に歩む“しなやかな組織”――信頼と柔軟性で支えるチーム運営
現在、経営者として何年ほど活動されているのでしょうか。
会社設立は2024年3月ですが、個人事業の時期を含めると約5年になります。経営を通じて痛感したのは、「人」と「お金」の難しさですね。設立当初は、仲間への感謝を形にしたい一心で福利厚生を手厚くしましたが、事業の基盤が整う前に負担が重くなり、持続性の重要さを学びました。経営とは理想だけでなく、継続のためのバランスを取ることでもあると感じています。
経営を通じて意識が変わった部分はありますか。
会社は、メンバー全員が理解し合い、支え合うことで初めて成り立つものだと気づきました。だからこそ「必ず成果で応える」「結果を出して還元する」という姿勢を大切にしています。チームの努力をきちんと利益として返せるように、自分自身が常に先頭に立って動くよう心がけています。
社員の方々とのコミュニケーションで意識していることはありますか。
弊社はフルリモート体制で、全員がオンラインでつながっています。そのため、相手の状況が見えづらい分、“無理をさせない”という方針を徹底しています。納期や目標は明確にしますが、過程ではプレッシャーをかけすぎず、困ったときにはすぐ相談できる雰囲気づくりを大切にしています。結果を追う責任は共有しつつも、働きやすい環境を守る。それがベンチャー企業としての柔軟性だと思います。
現在の組織体制についても教えてください。
かつては業務委託を含めて30名以上で運営していましたが、現在は5名体制でコンパクトに動いています。少人数体制で意思疎通が速く、各自が自分の役割を理解しているため機動力が高いです。開発や営業、経理なども垣根を越えて共有し、全員が数字や目標を意識して動けるチームづくりを進めています。信頼関係を軸に、少数精鋭で成果を出すことが今のGeniusystの強みです。
技術の力で産業構造を変える――次の10年に描く成長ビジョン
現在は5名体制で運営されているとのことですが、今後のビジョンを教えてください。
今は受託開発事業を中心に、堅実に売上と事業規模を拡大している段階です。今後2〜3年でさらなる事業拡大を図り、会社としての信用とブランドを確立していきたいと考えています。弊社の強みであるノーコード開発を中心とした開発手法は、複数案件を同時に進めながらも高品質を保てる点にあり、この優位性を活かして事業規模を一段と引き上げていく計画です。
その先の長期的な目標はどのように描かれていますか。
近い将来には、受託開発で築いた収益基盤をもとに、自社開発・技術開発の比率を高めていく方針です。最終的には、自社の製品・技術を通じて社会に新しい価値を生み出す「技術開発型企業」へと進化させていきたいと考えています。AIやクラウドを中心に、コンピュータの構造そのものを変えるような挑戦を続け、10年以内には社会実装を実現することを目標にしています。
組織拡大の方針についても伺えますか。
開発体制は少しずつ拡大しつつ、エンジニアを中心に約9〜10名規模のチームを目指しています。ただし、組織を大きくすることが目的ではありません。事務や経理など、専門的なバックオフィス業務は外部のプロフェッショナルにも協力を仰ぎ、柔軟な連携で運営していく考えです。
今後の経営において、大切にされたいことは何でしょうか。
一人ひとりが安心して力を発揮できる環境を整え、挑戦を楽しめる組織文化を築くことです。事業を拡大する中でも、常に「技術を通して社会に貢献する」という原点を忘れずに進みたい。Geniusystとしての使命は、テクノロジーの力で人と社会の未来をより良くすること。そのための挑戦を、これからの10年、そしてその先の未来で形にしていきたいと思っています。
経営もものづくりも“楽しむ心”から――日常にある探究の時間
経営以外で、リフレッシュや趣味として取り組まれていることはありますか。
実は、経営そのものが私にとっての趣味のようなものです。会社を動かすという日常の中に、常に課題と発見があるので、仕事をしている感覚より“創っている”という感覚が強いですね。”ものづくり”に近い感覚で楽しみながら経営しています。経営が楽しくなければ、経営者という仕事はプレッシャーや向き合うべき課題も多く続けられないですね(笑)
まさにその通りだと思います。
とはいえ、仕事以外の完全なプライベートの時間も大切にしています。たとえば、オーディオ機器を揃えてクラシック音楽を聴いたり、季節の風を感じながらドライブに出かけたり。特に冬の手前の少し冷たい空気の中で、窓を開けて走る時間が好きです。心が整理されるような感覚がありますね。
また、趣味の延長として、自分の業務を効率化するためのプログラムを組んだり、ちょっとしたツールを自作することもあります。世に出すものではなく、あくまで自分のための“便利道具”ですが、ものづくりが好きな性分なので、気づけば夢中になっていることが多いです。
最後に、「経道」をご覧になっている読者の方へメッセージをお願いします。
経道を拝見していると、同じように挑戦を続けている経営者の方が多いと感じます。もし本記事を通して、Geniusyst株式会社の取り組みや技術に共感してくださる方がいらっしゃいましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。共に新しい価値を創り、未来を変えていく仲間として、力を合わせていけたら嬉しいです。