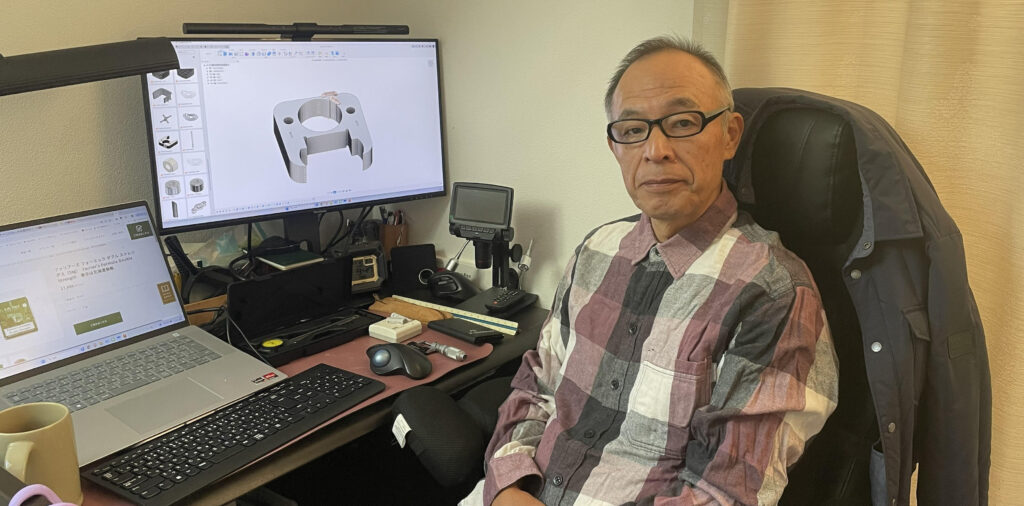長年にわたり自動車メーカーでエンジンの設計を担い、数多くの開発現場を経験してきた山口文博氏。退職後はその技術力を社会に還元するべく、「FKエンジニアリングサポート」を立ち上げました。一般の方の発明アイデアの具現化から、中小企業の新製品開発・品質改善・CE認証取得支援まで、幅広い“ものづくりの悩み”に寄り添う同社。エンジニアとしての誇りと仲間との協働を軸に、技術で人の挑戦を後押しする山口氏の想いと歩みについて伺いました。
目次
技術で“できない”をなくす――個人と企業に寄り添う“ものづくり支援”
現在の事業内容について教えてください。
当社では「技術の力で人と企業の挑戦を後押しすること」を理念に掲げ、個人支援と企業支援の2軸で事業を行っています。ひとつは、主婦やサラリーマンなど一般の方の発明アイデア製品化をサポートする事業です。製品化にはアイデアブラッシュアップ・図面化・試作・試験・量産など専門的な工程が必要ですが、多くの方がその手前でギブアップしてしまいます。当社はその技術面を補い、発明アイデアが形になるまで伴走しています。
もう一つは中小企業向けの技術支援です。開発部門が小規模、あるいは存在しない企業も多く、自社だけで新商品開発を進めるのは容易ではありません。当社では技術的な助言に加え、製造工程の不具合改善や品質向上など、現場に踏み込んだサポートも行っています。単なる外部委託ではなく「社内で自走できる体制づくり」を重視している点が特徴です。
CEマーキングのサポートとはどのようなものですか?
ヨーロッパで製品を販売するにはCEマーキングが必要ですが、小規模な企業にとって書類作成や安全証明の準備は大きな負担となります。当社では、エンジニアが自動車分野で培った認証経験をもとに、必要な情報整理や効率的な手順など実務面を支援しています。多くの製品は「自己宣言方式」で認証可能ですが、すべての構成部品の材質や含有物質の証明を揃える必要があり、中小企業には難易度が高い領域です。当社が最短ルートで取得できるよう伴走します。
これまでのサポート事例を教えてください。
家庭用水素製造機を扱うメーカーのヨーロッパ展開を支援した事例があります。部品表の整理、部品の有害化学物質適合証明収集、基準適合の整理、販売先での対応まで全工程をサポートしました。挑戦を断念する企業が多い現状を実感した案件であり、当社は「技術的な理由で挑戦が止まらない環境」を整えることを使命としています。今後も専門知識を活かし、企業の新たな市場挑戦を後押ししていきます。
“技術で人の夢を支える”という原点――ものづくり人生から見えた使命
この事業を始められた背景を教えてください。
事業の原点は、前職時代に続けていた自身の発明活動にあります。大学時代から馬術部に所属し、その後も馬具の改良を考案して特許出願を行っていました。その過程で弁理士の方に相談した際、「特許を取ったものの、量産化の方法が分からず困っている個人は多い」という話を聞き、強い問題意識を持ちました。専門知識がないまま業者に依頼して希望どおりにいかなかったり、必要以上の費用を支払ってしまう例もあると知り、「技術があれば助けられる人がいる」と感じたことがきっかけです。長年の設計経験から材料選定や性能とコストとのバランスを判断する力が身についていたため、それを活かして仲間のエンジニアと支援活動を始めました。その後、早期退職制度を機に独立を決意。「好きな技術に時間を使いたい」という思いに加え、大きな設備や仕入れの原資を必要としない事業形態であったことも後押しになりました。技術とパソコン、そしてノウハウがあれば挑戦できる。そのシンプルさが現在の事業につながっています。
前職での経験はどのように生きていますか?
前職の本田技術研究所では、量産車のエンジン設計を担当し、性能・安全性・コストの最適化を徹底的に追求してきました。この積み重ねが、今の製品開発支援における判断力の基盤になっています。また、不具合対応で現場に向かい原因を探る経験や、多くの部品メーカー様と協働して仕様を詰めていった経験は、「課題を見極める視点」と「対話で解決策を見つける力」として生きています。
個人支援と企業支援を両立している理由は何でしょうか。
個人の方はアイデアが素晴らしくても量産の壁に悩むことが多く、私は「夢を形にするお手伝い」という姿勢で負担をかけずにサポートしています。一方で企業支援ではいただいた対価を設備投資に充て、そこで揃えた測定機や加工機が個人支援にも活用されるという循環が生まれています。企業では実現性と効率性を重視し、個人では自由な発想に触れられる。双方を手がけることで視野が広がり、技術者としてのやりがいにもつながっています。
“一人ではつくれないものづくり”を支える――協働と信頼で育てるエンジニアチーム
経営を始めて感じたこと、特に印象に残っている点を教えてください。
本格的に売上が立ちはじめたのはここ数年ですが、実際に経営と向き合ってみて強く感じたのは、「技術」と「経営」はまったく別の専門領域だということでした。特に確定申告や帳簿付けのような事務作業は、前職では経験がなく、最初の一年は税務署に通いながら一つずつ覚えていきました。今では慣れましたが、世の経営者は皆これをこなしているのかと驚いたほどで、企業を運営する大変さと奥深さを実感しました。ただ、当社は仕入れや在庫を持たない形態のため事務処理が比較的シンプルで、外部の力も借りながら無理なく続けられています。
事業を進めるうえで、どのようにチームを組んでいったのでしょうか。
独立を考え始めた頃から、一人の専門性では対応できる範囲に限りがあると感じていました。そこで金属加工、電気設計、樹脂成形、品質改善など、多分野のエンジニア仲間に声をかけ、互いの強みを生かし合える体制をつくりました。現役の技術者もいれば、定年後に経験を活かしたい方、部品メーカー出身者もいらっしゃって、案件に応じた最適な組み合わせで進められるのが強みです。私はその中心で“技術コーディネーター”として全体をつなぎ、前職で培った対話力や品質監査の経験が、今の連携の土台になっています。
エンジニアの方々とのコミュニケーションで意識していることはありますか?
大切にしているのは、こまめなWEB会議による情報共有と、試作品を囲んで議論する時間の両方を確保することです。コロナ禍でリモート環境に慣れたこともあり、オンラインでの連絡はスムーズに行えています。一方で、試作品は実際に手に触れ、強度や質感を確かめながら議論することが不可欠です。また、協力してくれるメンバーには必ず対価を支払い、技術者としての誇りを持って関われる環境を整えています。こうしてお互いが気持ちよく働ける関係性を保つことが、強いチームづくりにつながっていると感じています。
“求められる技術者”であり続けるために――広がりゆく依頼の中で描く未来像
今後のビジョンや、事業として目指していきたい方向性を教えてください。
独立当初は、個人発明家のサポートが中心の“街の技術相談所”のような存在でしたが、現在は口コミによって企業・個人を問わず幅広い相談が寄せられるようになりました。そのため、明確に事業領域を限定するのではなく、「どんな依頼に対しても、自分の専門性で応えられる範囲を広げていくこと」が今のビジョンにつながっています。ハードウェア領域は分野ごとに求められる技術が大きく異なりますが、材料・構造・製造といった基盤技術は共通です。これまでの経験に加え、仲間のエンジニアの専門分野を組み合わせることで、“技術で応えられる領域”をさらに広げていきたいと考えています。
依頼が増える中で、どのような姿勢で仕事に向き合っていきたいと考えていますか?
目の前の依頼に誠実に応える姿勢を最も大切にしています。「こんな製品はつくれますか?」という素朴な相談に対し、実現可能かどうかを丁寧に見極め、可能な場合は最後まで伴走する。そんな積み重ねが信頼につながっています。難易度が高い案件でも、適切なエンジニア仲間と連携することで解決策が見えることも多く、技術者同士のネットワークは今後ますます大きな力になると感じています。
事業の将来をどのように考えていますか?
具体的に「この領域に進出したい」という目標を掲げているわけではありません。むしろ、どんな相談が来るのか分からないからこそ面白く、そのたびに新たな発見があります。だからこそ、常に自身の守備範囲を磨き、無理なく新しい知識を吸収し続ける姿勢を大切にしています。「頼んで良かった」と感じていただける仕事を積み重ねることで、結果的に未来が形づくられていくと考えています。これからも求められるご要望に応えながら、できることの幅を広げていく。その歩みが、新しい挑戦や出会いにつながっていくはずです。
“馬と向き合う時間”が創造力を育てる――技術者を支える大切なリフレッシュ法
お仕事以外で熱中されている趣味やリフレッシュ方法はありますか?
大学時代に所属していた馬術部をきっかけに、今も週に数回は乗馬クラブへ通い続けています。机に向かう時間が長い技術の仕事だからこそ、自然の中で馬と向き合う時間は貴重なリセットの機会です。馬の呼吸やリズムに合わせて体を預けていると、不思議と頭が整理され、仕事で抱えていた課題にも新しい視点が浮かんできます。心身ともに整う、欠かせない習慣になっています。
馬具づくりも続けているそうですね。
乗馬を続ける中で、「もっと快適に」「もっと安全に」という思いから、馬具の改良や新しい道具の試作を続けています。素材選びや構造の工夫など、こうした取り組みは特許出願にもつながった経験であり、現在の事業の原点にもなりました。今でも新しい馬具を試すことは、エンジニアとしての感性を磨く大切な時間です。
馬術は現在の仕事にも影響していますか?
馬術は人と道具だけで成立するスポーツではなく、馬という意志を持つ相棒が関わる唯一のスポーツです。それゆえ馬術では“相手に寄り添う姿勢”が何より重要で、そのスタンスは企業や個人の依頼に向き合う際にも大きな影響を与えてくれています。少しずつ調教を積み重ねて成果へ近づく感覚は、試作品を重ねて完成度を高めていく開発の仕事と同じです。馬と過ごす時間は、技術者としての軸を整える大切な習慣であり、ものづくりに対する姿勢を常に原点へと戻してくれます。
これからも、馬と向き合う中で得た学びや感性を大切にしながら、依頼してくださる方々の挑戦に寄り添い、技術者として誠実にサポートし続けていきたいと思います。