大学発ベンチャーが挑むパワー半導体の未来――原理原則で磨く技術と連携力
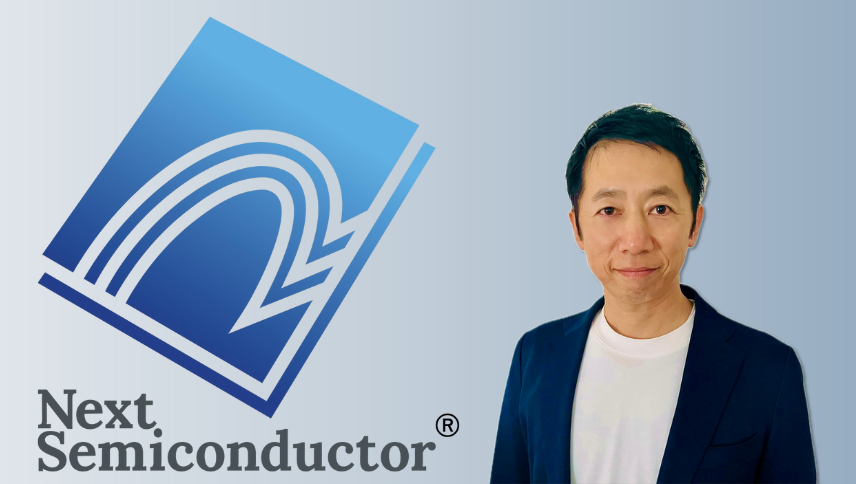
株式会社Next Semiconductor 代表取締役CEO 松本 武弥氏
国立大学の研究室を母体に生まれた株式会社Next Semiconductorは、パワー半導体を核に技術コンサルティングから開発支援、自社製品化までを一気通貫で進める大学発ベンチャーです。今回は、三本柱の事業内容や分散協業の仕組み、今後の成長戦略について代表の松本氏に伺いました。
技術を事業に接続する“三本柱”
――現在の事業内容と特徴を教えてください。
第一に、パワー半導体デバイスからパワーモジュール、ゲートドライブ回路までを対象にした技術コンサルティングを行っています。第二に、新製品の試作・検討など技術開発の支援です。第三に、自社製品の開発で、現在はGaNを用いたパワーモジュールに注力しています。大学の研究成果をコアに据えつつ、企業の事情や現場の制約に合わせて“使える形”に落とし込む点を重視しています。モーター、電力変換、電池、ロボット制御など周辺領域の他の大学発ベンチャー企業・研究者とも連携し、一台の自動運転車を構成できるほどの技術範囲をカバーできるのが強みです。
経営者としての原点と価値観
――独立の経緯と、大切にしている価値観を教えてください。
複数企業で経験を積み、最先端の大学研究成果を社会に実装したい思いが高まり、2020年に大学発ベンチャーの世界に飛び込みました。当社は2022年の創業です。価値観の軸は「社会益に資するか」「将来につながる技術か」です。流行や個別企業の思惑に流されず、原理原則で判断します。技術者育成にも力を入れており、企業の技術者養成のみならず、小中高生の半導体教育や大学生向け講義を通じて、将来の担い手を増やす活動にも力を入れています。人材の裾野を広げることが、結果的に日本の産業競争力の底上げにつながると考えています。
小規模×連携で生むスピードと柔軟性
――組織運営やコミュニケーションの工夫は。
現在、当社メンバーは5名ですが、外部の連携するベンチャー企業や専門家と密に連携し、案件ごとに最適チームを編成します。案件の多くは大学や提携企業からの紹介です。少数精鋭ゆえに一人ひとりの裁量は大きく、役割の壁を越えて議論・実装まで一気に進める文化です。営業は課題と捉えていますが、論点整理と技術説明の質を高め、受注後の“フラットな意思疎通、原理原則に沿った技術情報の共有”で信頼を積み重ねています。
市場選定と成長計画――高耐圧大電流領域でGaNの社会実装へ
――注力市場と成長計画を教えてください。
電動モビリティや再生可能エネルギー、データセンター向けの電源需要領域に注力します。電力変換効率の向上が求められる分野で、GaNの特性を生かせます。資金は補助金・融資を活用しつつ、自社製品の展開で収益基盤を強化します。海外展開も視野に、製造はパートナーと連携し、当社は高付加価値の研究開発に集中します。研究室母体の独立資本だからこそ、遠回りに見えても確かな技術の実績を積み重ね、確実に社会実装へつなげます。
あわせて、製品化の前段として試作組立機を整備し、解析、評価装置の内製化を進めています。設計から試作・評価・フィードバックまでのリードタイムを短縮します。パワーデバイスや重要素材は国内外のパートナーと連携し、アプリケーションに合わせた最適解を探ります。さらにアプリケーションノートや評価ボードの提供を強化し、顧客の設計立ち上げを省力化。再エネ設備や電動モビリティ関連設備での共同実証も拡大し、実運用前提のPoCで価値を可視化していきます。
仕事が趣味、でも“手と身体”で整える
――リフレッシュ方法や、仕事に活きる視点を教えてください。
仕事そのものが趣味ですが、他にはレストアした古いオートバイと長く付き合っています。最近では自らの手でオーバーホールに取り組んでいます。分解・調整・再組立のプロセスは、製品開発にも通じる面白さと奥深さがあります。身体づくりではフルマラソン、ボクシングやキックボクシングにも取り組んでいます。経営者仲間と汗を流す時間は、肩書を外した“拳と拳、気持ちと気持ち”のぶつかり合い。それを通じた集中力と判断力を、日々の経営と意思決定にそのまま持ち込みます。
――最後に、近い将来の到達点を一言でお願いします。
高耐圧大電流領域でのGaNパワーモジュールの社会実装を実現し、再エネや電動モビリティ領域で「高効率の領域」を塗り替えたいです。大学の先端基礎研究で生まれた技術を、社会の当たり前へ――その歩みを、確実に進めます。












