研究者の視点から社会課題を解決する新たな挑戦
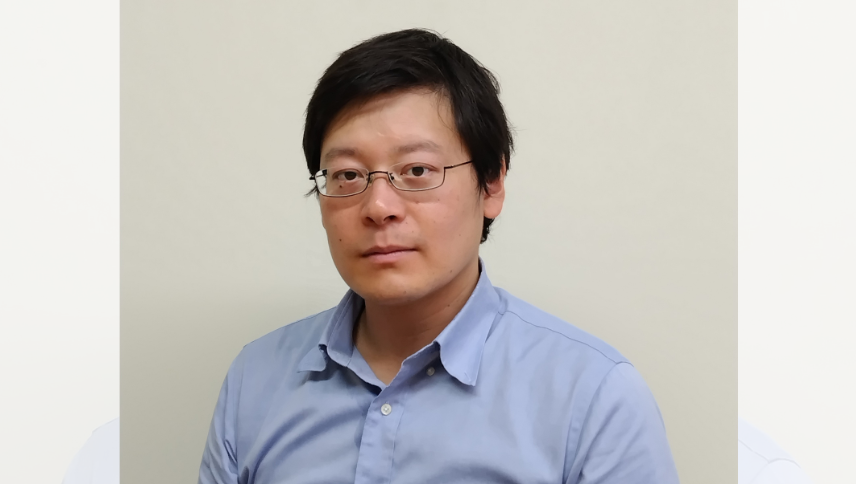
ORRELS株式会社 代表取締役 井上 祐樹 氏
大学研究者として活動しながら、自らの研究成果を社会に実装するために企業を立ち上げた井上氏。大学院生時代に芽生えた「大学での研究成果が社会でより活かされる仕組みをつくりたい」という思いを原動力に、研究成果の社会実装を促す場や大学院進学への機会提供を促す仕組み作りに挑んでいます。今回は、事業立ち上げの経緯や理念、直面する課題、そして今後の展望について伺いました。
研究者の立場から始めた新しい挑戦
――御社の事業内容と設立の経緯を教えてください。
本職は大学教員で研究者です。博士課程に進学する際、日本の産業競争力の低下を目の当たりにし、技術イノベーションを起こす仕組みを科学的に研究する道を選びました。特に「エコシステム」の形成に関心があり、プラットフォームとその周辺の関係者が市場を育てる仕組みを研究してきました。
その成果を本でまとめたものの、実社会で応用されなければ意味がないと考えました。そこで、研究者が社会で活躍できる仕組みをつくることを目的に起業したのです。研究者の活動を社会へ橋渡しするサービスと、研究者を増やす意味での大学院進学支援に関連するサービスを主に展開しています。
社会と、研究機関としての大学とを接続する仕組みをつくる
――具体的にはどのような課題に取り組んでいるのですか。
大きな課題の一つは、現状では大学の研究成果が社会で活用されるかは、運に大きく左右されていることです。研究成果は論文という形で発表されますが、そこから事業として活用されるまでには距離があります。特にその分野に精通する研究者以外が、論文で主張されている知的な革新性を把握し、それを事業と結びつけることは困難です。
この課題を解決するために、研究者自らが研究成果の価値を紐解き、事業への橋渡しに関する情報を提供したり、あるいは研究成果を活かしたサービスを自ら展開する場の提供を行っています。
もう一つは、研究者の入口としての大学院進学が、なかなか選択肢に入らない現状です。特に文系では研究室文化がなく、殆どの学生がそのまま就職してしまいます。社会人が進学を考えても何から始めていいかが分からず、入り口でつまずくケースも少なくありません。
こうした課題を解決するため、オンラインで全国どこからでも、大学院進学に必要な各種情報や有用なツールを得ることができる仕組みを開発しています。大学教員という立場のため、塾や予備校のようなサービスを展開することはできませんが、研究者ならではの本質をついた情報提供と仕組み作りを目指しています。
経営者としての原点と決断
――経営者になろうと思われたきっかけを教えてください。
学生時代は経営に興味はありませんでした。しかし研究を進める中で「理論を社会に出すこと」に強く惹かれるようになりました。出版だけでは届かない層が多く、ならば自分で事業化しようと考えたのです。
加えて祖父が経営者であったことも、心理的なハードルを下げました。本業が大学教員であるため経営に専念することは困難ではありますが、研究者としての使命感が創業を後押ししました。
持続可能な組織を模索する日々
――現在の組織運営や課題について教えてください。
専任は私一人で、数名の非常勤役員が兼業で関わっています。専門性を持ち寄る体制は強みですが、人手不足は大きな課題です。特にデザインや営業面のリソースが不足しており、大学教員という立場上、本業の勤務時間中に動けない制約もあります。
とはいえ、研究者の視点で設計するサービスは共感を得やすく、少しずつ協力者が増えています。研究を社会に届ける取り組みは一人では不可能だからこそ、仲間を広げながら持続可能な組織へ育てていきたいと思っています。
新たな市場を切り拓くビジョン
――将来の展望について教えてください。
目標は二つあります。第一に、研究成果を社会に、特に産業に結び付けるための、確かなルートを生み出すことです。大学の研究成果を社会に結びつける事業はいくらかありますが、研究者の間で標準的になっているものは私が知る限りありません。関連する事業も、理系の先進的な技術に注目したものがほとんどです。
私は、理系・文系問わず、あらゆる研究成果には事業化の可能性があり、そこにはイノベーションの種が眠っていると考えています。自身の研究成果を社会で役立てたいと研究者が考えたときに、それが実現できる場の確立を目指していきます。
第二に、大学院進学者を増やすこと。特に文系や社会人の進学への道を拡大したいです。進学者を増やすうえでは、そこに市場が形成されているかどうかは重要です。大手予備校による各大学へのブランディング活動は大学関係者の間では賛否両論あるものの、大学進学への拡大に肯定的な影響を与えていることは確かです。一方で日本人向けの大学院受験市場は、現状ほとんど存在していません。学部教育に劣らない、大学院教育の価値への認識を社会に広め、市場を成立させることで、大学院進学者を増やしたいという想いがあります。
私が大学教員という立場のため、当社が直接予備校を展開することはできません。そのため、大学院進学へのハードルを下げ、機会を提供する活動を行うことで、市場が拡大するための種まきをしていきたいと考えています。
研究と育児の狭間で
――プライベートのリフレッシュ方法について教えてください。
0歳と4歳の子育て中で自由な時間はほとんどありません。休日は子どもを公園に連れて行くことが一番のリフレッシュになっています。かつてはランニングやゲームも楽しんでいましたが、研究を進めること自体が楽しいので、今は研究そのものが気分転換でもあります。
育児や本業と両立しながらの経営は容易ではありませんが、仲間を増やしながら少しずつ形を整えていきたいと思います。












